都立入試対策・国語
Ⅰ.過去10年間の平均点の推移
◆(表Ⅰ-ⅰ)過去10年間の国語平均点 ※点数は東京都教育委員会の発表による
| 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 |
| 61.6点 | 60.5点 | 69.5点 | 65.9点 | 60.9点 |
| 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 |
| 69.0点 | 63.8点 | 65.2点 | 55.7点 | 62.9点 |
| 平成16年度 | ― | ― | ― | ― |
| 69.7点 | ― | ― | ― | ― |
Ⅱ.出題概要
◆(表Ⅱ-ⅰ)試験概要
| 試験時間 | 合計点 | 大問数 | 総小問数 |
| 50分 | 100点 | 5問 | 25問 |
◆(表Ⅱ-ⅱ)出題構成
| 形式 | 配点 | |
| 大問1 | 漢字の読み (小学高学年~中3履修範囲) |
10点(各2点×5問) |
| 大問2 | 漢字の書き取り (小学高学年~中3履修範囲) |
10点(各2点×5問) |
| 大問3 | 文学的文章を読解する問題 ⇒選択肢4題+記述1題 |
25点(各5点×5問) |
| 大問4 | 論説的文章を読解する問題 ⇒選択肢4題+作文1題 |
計30点(各5点×4問+作文10点) |
| 大問5 | 古典を用いた随筆文 ⇒選択肢3題+記述2題 |
25点(各5点×5問) |
(時間・点数・出題構成に関するコメント)
「日本語」だから何もしなくても大丈夫という先入観を捨てよ!
国語という科目は、多くの受験生たちによって、「日本語だから、特に何も準備をしなくても何とかなる」といった”奇妙な共通認識”があり、受験勉強の中でも軽視されているといって過言ではありません。また、漢字や語句の知識の習得を除けば、「どのように対策をしたらよいか」など、明確なマニュアルが存在しているとも言い難いのも事実です。都立入試について言及すれば、「解法のテクニックとパターン」をマスターし、過去問演習に慣れることが、「合格への近道」となるわけです。
Ⅲ.単元ごとのポイント解説
大問1・2 漢字の読み・書き
漢検3級は取得せよ!
実際の出題範囲を過去問を通して分析してみると、漢字の読み・書き取り問題共に小学校高学年から中3履修漢字レベルの基本的な漢字力を問う良問になっています。漢検3級取得者や学校の定期試験で、しっかりと漢字練習をして点数を取っている受験生であれば、入試で一番の得点源になり得る問題といえる。また、「過去問において出題歴のある漢字」が再登場したこともあり、20年間分程度の漢字の過去問は確実に解いておくとよい。(修明塾では塾生に過去問漢字テストを実施しています)
大問3 小説・物語
選択肢の問題が多いのが特徴
ただし、今後は記述式問題が増えていく可能性があります。
(近年の出題例)
①主人公や登場人物の様子(動作など)を答える。
「-----とあるが、この表現から読み取れる○○の様子について述べたものとして適切なものはどれか」
②主人公や登場人物の動作の理由を答える。
「-----とあるが、○○がこのように思ったわけとして適切なのはどれか」
③ある場面においての主人公や登場人物の心情や気持ちを答える
「-----とあるが、このときの○○の気持ちに近いのはどれか」
④文章の表現(描写・背景)について答える
「-----とあるが、この表現について述べたものとして適切なものはどれか」
(記述問題)字数制限のあるもの
主人公や登場人物の立場に立って、その場面においての気持ちを「話し言葉」を使って表現する。
「この文章を読んで、あなたが○○だとして、△△に対する○○の気持ちを伝えるとしたら、
どのように言うか。あなたの話す言葉を□□字以内でまとめよ」
→どのように読解したら、正答になる記述ができるか?
○主人公や登場人物のそれぞれの動作と気持ちを結び付けて読むことが必要です。
→文章に線を引いたり、囲んだりして、主人公・登場人物の「動作や心情の関係性」をまとめる
⇒出題につながる選択肢は消去法で解くことは必須です。
「ア~エの4択の文をじっくり読んでいくと、
実は、『文中の事実とは異なる記述や表現がある』ことに気付きます。」
それを一つずつ丁寧に見つけていくと最後に1つだけ、正しいものが残ります。
本文を丁寧に時間をかけて読むことが、選択肢の絞り方・正答率を
飛躍的に向上させます。
これは、次の大問4の説明文・論説文の出題においても「共通した解法」です。
大問4 説明文・論説文
選択肢+記述+作文
(近年の出題例と表現)
①テーマ内容に対する事実関係を断定した理由・背景についての問題
「-----とあるが、筆者がこのように述べたのはなぜか」
理由や根拠を探る「~だから」「~と考えられる」など
②文章表現に対する理解を問う問題(読解力の判定)
「-----とあるが、○○とはどういうことか」
⇒文の表現についての詳しい説明
対策 意味や解釈をおさえておく
③文章構成における段落関係についての問題
例)「第○段落は文中でどのような役割をしているか」
④テーマ作文(200字作文)
必ず入試問題四に関係したり、文中の表現などについて取り上げ、200字以内で自分の感想・主張または体験を書く。
例)「この文章を読んだ後、○○というテーマで具体的な体験を示して意見発表をするとき、
あなたの話す言葉を書きなさい」
今後は記述式問題が増えて、難易度が上がっていく可能性があります。
大問5 古典を用いた随筆文
筆者による古典(古文・漢文)を引用した文を含むの解釈文から出題されます。
そのため、他県の公立高入試問題や私立高の入試問題に見られる「典型的な古典の出題」にはなっておらず、
受験生にとっては、
傾向→口語訳や書き下し文や古典知識・表現などを答えるのはほぼない。
(近年の出題例)
①現代語の表現についての意味
○国語辞典で確認できるレベル
○文脈に合わせた解釈の場合
「-----とあるが、これと同じ意味・用法に近いものはどれか」
「-----とあるが、これと同じ意味・用法で----を用いて、○○字以内で文を作れ」
②文中からキーワードや重要表現などを探し出す、あるいは理解を問う問題
「-----について説明したものとして適切なものはどれか」
「-----とあるが、○○とはどういうことか」
⇒文の表現についての詳しい説明
対策 意味や解釈をおさえておく
③原文中から「~」に当たる言葉を抜き出す問題
「-----という部分に相当する箇所を、原文中からそのまま抜き出せ」
④テーマ内容に対する事実関係を断定した理由・背景についての問題
「-----とあるが、筆者がこのように述べたのはなぜか」
理由や根拠を探る「~だから」「~と考えられる」など
以上の出題傾向・パターンに合わせて、修明学園の中3受験生の国語の授業では、
都立入試で得点を向上させる読解法を徹底してマスターさせています。
国語こそ、「解き方」をしっかり定着させれば、短期間で成果が出る科目です。

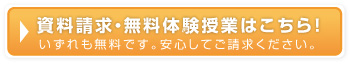
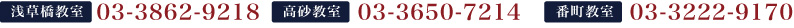
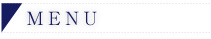
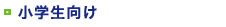
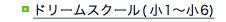
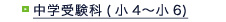
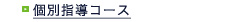

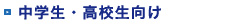

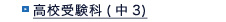
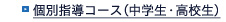


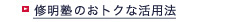


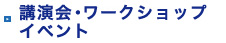







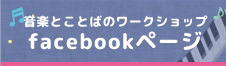
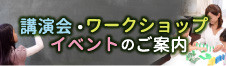
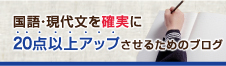
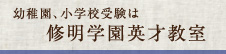
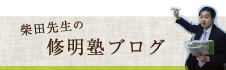
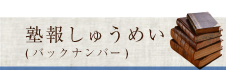
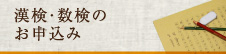
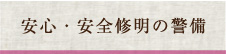
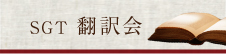
 お問い合わせ
お問い合わせ