都立入試対策・英語
Ⅰ.過去10年間の平均点の推移
◆(表Ⅰ-ⅰ)過去10年間の英語平均点 ※点数は東京都教育委員会の発表による
| 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 |
| 53.7点 | 62.3点 | 58.1点 | 58.9点 | 49.9点 |
| 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 |
| 54.2点 | 50.8点 | 56.0点 | 59.9点 | 51.3点 |
| 平成16年度 | ― | ― | ― | ― |
| 55.4点 | ― | ― | ― | ― |
Ⅱ.出題概要
◆(表Ⅱ-ⅰ)入試概要 50分 100点
| 大問数 | 総小問数 | 総語数 | 時間/問 | 語数/分 | 点数/問 |
| 4題 | 23問 | 約1700語 | 2分 | 34語 | 約4点 |
◆(表Ⅱ-ⅱ)出題構成
リスニング問題がH9年度から導入、H15年度以降、英作問題が大問2に移動して、現在(H24年度)の出題構成に至る。
| 形式 | 配点 | |
| 大問1 | リスニング問題 問題A 対話文 問題B 文章 |
20点(4点×5問) |
| 大問2 | 1資料・適語選択 2資料・適語選択 3(1) 内容真偽 (2) テーマ作文 |
4点 4点 (1)4点 (2)12点 |
| 大問3 | 読取・適文選択 読取・適語補充 要旨・適語選択 |
28点(4点×7問) |
| 大問4 | 読取・適文選択 読取・適語補充 文脈整序 内容真偽 一致・適文選択 英問英答 |
28点(4点×7問) |
(総括:時間配分・得点配分・総語数について)
英語は50分、100点満点のテストとなります。例年、大問4題、総小問数は全部で23問と安定した出題どなっています。単純計算で1問にかけられる時間は2分強、小問1問あたりの配点は4点となっています(自由英作1問を除く)。自由英作のみ1問12点の配点となっており、自由英作は得点にして、3問分の価値があり、理論上は6分かけても良い問題となります。
(出題構成に関するコメント)
例年、H15年度からは安定した出題構成となっており、全体として「リスニング=聞く力(20点分)」「長文=読む力(68点分)」「英作=書く力(12点分)」から出題がされています。その一方で都立英語の最大の特徴は、単語や文法の知識を問う問題がほとんど出題されない点です。この点に関しては東京都教育委員会の出題方針(「初歩的な英語を聞いたり読んだりして、話し手や書き手の意向などを理解するとともに、自分の考えなどを表現する実践的コミュニケーション能力をみる」)が大きく反映されているように思います。都立英語では断片的な知識(単語力や文法)はほとんど問われません。実践的な技能を重視している姿勢は、リスニングや終始徹底した長文構成、英作においても和文英訳ではなく英文を創作させるという点に表れています。
Ⅲ.単元ごとのポイント解説
【Ⅲ-1:リスニング問題-聴く力】
ここではリスニング問題の要点を記しておきます。
○リスニング問題が始まる前に
・答えの選択肢が事前に示されている場合には、必ず目を通しておくようにしましょう。
(選択肢が単語の場合)―これらは質問内容の想定に役立ちます。例えば4つの選択肢がそれぞれ人の名前であったとしましょう。その場合、「誰が」という部分が重要になってくることは想像に難くありません。十中八九、質問文はWhoの疑問詞で始まることでしょう。4つの選択肢が時間に関するものならWhen、場所に関するものならWhereの質問文など、問われている5W1Hを念頭に置いて、1周目からある程度ポイントを絞ってリスニングに臨むことができます。ただし、後述するように1周目にポイントはリスニング全体の流れをおさえる事にあるので、ポイントの絞りすぎはお勧めしません。推測が外れた時に痛手が多すぎるからです。
(4つの選択肢が文章形式の場合)―この場合には質問文の5W1H の想定に加えて、さらにより多くの情報が得られることになります。4つの選択肢の中に出てくる単語は、ほとんどがリスニング文中に出てくる単語ですので、リスニング文の内容がある程度推測可能になってきます。例えば4つの選択肢が(ア 彼は学校へ行く イ 彼は授業を受ける ウ 彼は部活をする エ彼は帰宅する)だったとすると、これはある男の子の生活における行動・予定に関する話だろうと推測できます。先ほどと同じく行き過ぎた推測は先入観となり危険ですが、選択肢にある単語が読み上げられ、聞き取れるというだけで心理的にも大分落ち着くものです。
○リスニング1周目において心掛ける事
・リスニング文の全体の流れをおさえること
・質問をきちんと聞き取ること
1周目において大事なことはリスニング文の全体の流れをおさえること、質問をきちんと聞き取ることです。質問文を聞き逃せば2周目もポイントを限定できずに、1周目と同じ条件でリスニングしなくてはならなくなります。質問では5W1Hの何が聞かれているのかは必ず聞き取れるようにしておきましょう。1周目において、読み上げられる文章全体の流れをメモし、流れを大まかにでも押さえておくことができれば、質問の答えが全体のどの部分にあったか限定でき、ポイントに集中することができます。
○リスニング2周目において心掛けること
・2周目が読み上げられる前に、質問に対する答えが全体のどの部分にあるかを検討
・質問の答えにあたる詳細な情報までつけ加えるように聞いていく
2周目では、1周目で大まかにつかんだ流れに詳細な情報を肉付けしていく作業になります。答えにあたる部分が全体の中でどのくらいに流れてくるかきちんと心構えをしておき、肝心の答えの部分を聞き逃さないようにしましょう。
○対話文における技術
・2周目は質問で言及された性別(男・女)の声に集中する
これは問題Aにあたる対話文のリスニングにのみ使える技術ですが、対話文における2者の会話は男女間で行われることが多いことは覚えておいて損はありません。例えば一周目の質問文が男の人に関する質問であった場合、2周目は男の人の声で読み上げられる文章に集中すればよいということになります。男の人の声と女の人の声ははっきり違いが分かるので、使い勝手がよいのも特徴。ぜひ活用してみてください。
以上、リスニング問題にあたっての技術を記しましたが、普段の勉強におけるリスニング対策としては、月並みですが英語を聞きなれること以外にはありません。リスニング問題が苦手な生徒さんは意識的にCDを繰り返し聴くなどして英文に耳を慣らすこと、また英文を自ら音読する習慣をつけておくことも肝要です。英語のリズムだけでなく、英語と日本語の骨格は違うこと、それらを理解しておくだけでも大分違いがあるかと思います。
【Ⅲ-2:長文読解ー読む力】
リスニングを除いた英文の総語数はおよそ1400語(表Ⅲ-ⅰ)と公立中学校の教育課程のリーディング量(表Ⅲ-ⅱ)から比べると、非常に分量が多いと言えます。また長文読解に許された時間量から計算すると、300語程度の英文であれば、どんなに遅くても8分で読解かつ解答しなくてはならないという、読解力だけでなく一定以上のスピードも要求されていることが分かります。公立の教科書のみによる学習では、長文を読み慣れることはできず、長文読解力において致命的な習熟不足に陥ることは否めません。長文読解力の改善は割合時間がかかるので、早い時期から取り組みましょう。なお、(表Ⅲ-ⅲ)には最近5年間の大問2~大問4の語数の推移をのせています、参考になさってください。
◆(表Ⅲ-ⅰ)リスニング除く大問2~4までの概要 38分※80点 ※リスニング問題は12分と想定
| 大問数 | 総小問数 | 総語数 | 時間/問 | 語数/分 | 点数/問 |
| 3題 | 18問 | 約1400語 | 2分 | 37語 | 約4点 |
◆(表Ⅲ-ⅱ)公立中学校教科書 リーディング語数例
| NEW CROWN | NEW HORIZON | TOTAL ENGLISH | |
| READ1 | 300語 | 278語 | 298語 |
| READ2 | 385語 | 296語 | 454語 |
| READ3 | 422語 |
◆(表Ⅲ-ⅲ)大問2~4までの5年間の語数の推移・出題
| H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | ||
| 問2 | 1 | 96語 | 90語 | 87語 | 85語 | 107語 |
| 2 | 128語 | 111語 | 140語 | 91語 | 92語 | |
| 3 | 133語 | 159語 | 158語 | 155語 | 175語 | |
| 問3 | 441語 | 353語 | 343語 | 360語 | 399語 | |
| 問4 | 637語 | 621語 | 632語 | 634語 | 583語 | |
| 総語数 | 1435語 | 1334語 | 1360語 | 1325語 | 1356語 |
|
さて、出題に目を向けていきたいと思います。出題されている問題を再掲します。
・英問英答 (細部)疑問詞で聞かれた事柄に対しての答えを適切な位置から引用、英語で解答できる
・一致・適文選択 (細部)話の内容を理解しており、条件文から正しい文を選択できる
・内容真偽 (細部)話の内容を理解しており、各文の正誤を判定できる
・読取・適語補充 (前後のつながり)該当する場所が分かり、語句を代入できる
・読取・適文選択 (前後のつながり)指示語など前後の文脈のつながりを理解できている
・要旨・適語選択 (あらすじ)話の全体の流れを理解し、該当箇所から書き抜きできる
・文脈整序 (あらすじ)全体の物語の流れを理解している
複雑に書いてありますが、つまるところすべての問題は長文が読めているかどうか理解を問うているだけだと分かります。(細部)に関する問題から(あらすじ)に関する大まかな問題まで、バランスよく配置されてはいますが、東京都立最大の特徴は文法問題が意図的に出題されていないところにあります。(ただし、今年度からの新学習要綱の変更により文法が重視されるようになる可能性はあります。)
○長文読解のコツ
長文攻勢の東京都の都立入試においては、スラッシュ読みが非常に効果的であると言えます。スラッシュ読みとは意味のまとまりで区切り、前から順序を逆転させることなく訳していく読み方の事です。日本語と英語は訳す順序が違うことは言うまでもありませんが、一文一文を丁寧に頭の中で日本語訳に変換していっていたのでは、時間も足りなくなります。また都立入試では前後の文同士のつながりから長文全体にいたるまで、滑らかに話が理解できていることかどうかを問われているので、一文ずつに没頭してしまうと、どうしても話全体の流れを把握できずじまいになってしまいます。修明塾の受験科では、毎回の授業でスラッシュ読みを取り入れ、徹底的に英語脳を養うことを目的としています。英語を英語の順序のまま受け取るということは、英語のリズムや文法の理解にも役立ちますので、リスニングや英作など複数の単元において好影響を望むことができます。
ただし、思考転換にはある程度の時間がかかります。毎日辛抱強く、そして丁寧に取り組むことを心掛けて下さい。また、最初から難し過ぎる長文に手を出さないようにしましょう。
○英問英答問題
ここでは、つまづく可能性の高い英問英答問題について解説しておきます。まず、基礎知識として
・疑問詞のない文章→Yes/Noで受け答えが可能。
・疑問詞のある文章→Yes/Noによる受け答えは不可。
ですが、都立入試で問われる文章は基本的に後者となります。YesかNoで答えられない問題であるので、答えが一つに決まらないように思われますが、多くの場合答えは一つに決まります。
難易度が高いように思われる英問英答問題においても結局ほとんどの問題は対応箇所を聞いているだけ、だということを肝に銘じておく必要があります。自分で英文を1から作る必要はありません。質問文にあたる箇所を探し、質問に合うように少し変更をするので十分です。具体的には、対応箇所を見つけた後に、必要に応じて人やものを代名詞に変更してあげれば事足ります。動詞の時制による語形変化はたいてい文中と同じになります。疑問文では動詞が原型に戻っている点などに注意を払っておきましょう。
【Ⅲ-3:テーマ作文―書く力】
○自分の手持ちの単語・文法で表現する(妥協する)ことを覚える
H8までは和文英訳であったものが、H9からテーマ作文に変更されました。H15年度からH24年度にかけては、現在の大問2-3の位置に固定されています。都立入試はテーマ作文で最も自由度が高いのが特徴です。例えば、H23年度の出題には、「あなたが困っているときにだれかに助けてもらったことについて、英語で書くことになりました。あなたがだれかに助けてもらったことを一つ取り上げ、そのことについて三つの英文で書き表しなさい」とあります。その時、日本人としては当然ですが、日本語で頭の中で答えにあたる文章を構築し始めます。そして、難しいニュアンスを表現するために複雑な表現を選んでしまいます。答えに当たる文章を思い描いたにも関わらず手が止まってしまうのは、日本語の豊富な語彙で作った答えに対して、英語の貧弱な語彙・文法が追い付かないからです。
日本語の高尚な表現にあたる英語を作り上げようとするのではなく、表現したい内容を自分が知っている英語の語彙・文法で表現できるレベルまでに、似たような表現にする(近似化する)・削除する(言いたいことがあっても表現できないなら思い切って捨てる)のが正解です。英作では文学的な評価がなされるわけではありません。書いた3つの文章に誤りがなく、論理的なつながりが正しくさえあれば採点者は減点する余地がなくなるわけです。妥協を覚えましょう。同じ文に対して2通りの英訳を思いついた場合には正解だと確信が持てる英文を選びましょう。逆に言えば、和文英訳に対するテーマ作文の利点は、自分の手持ちの単語・文法で自由に表現して良いということです。和部英訳とテーマ作文には予想以上に難易度の開きがあります。英作の基本ができている生徒さんなら、短期間で修正可能ですので、冬休みに集中的に対策をしておくのでよいでしょう。
テーマ作文と和文英訳との差については、百聞一見にしかず、です。実際にテーマ作文特有の難点を体感し、一定期間集中して対策することにより、役に立つ表現・参考例文などの使える知識を自分の中に蓄積していくことが有効です。
【その他ー新指導要綱を受けて】
新指導要綱を受けて、覚える単語の量が増加し、教科書にも文法の解説が詳しく掲載されるようになりました。これを受けて、長文に出てくる単語の難易度の上昇、また設問にも文法の要素を取り入れた問題が出題されるかもしれません。

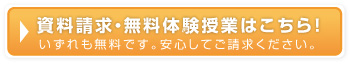
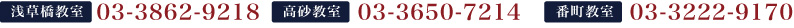
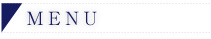
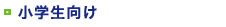
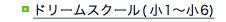
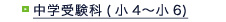
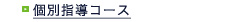

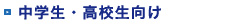

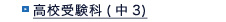
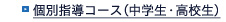


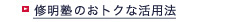


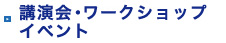







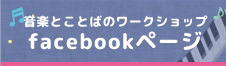
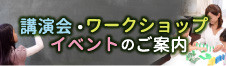
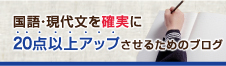
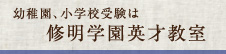
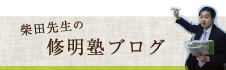
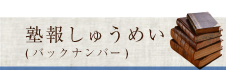
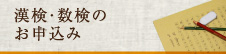
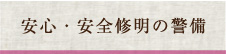
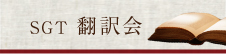
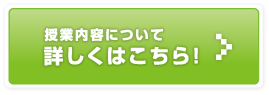
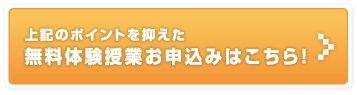
 お問い合わせ
お問い合わせ